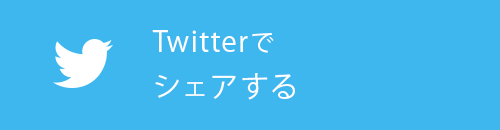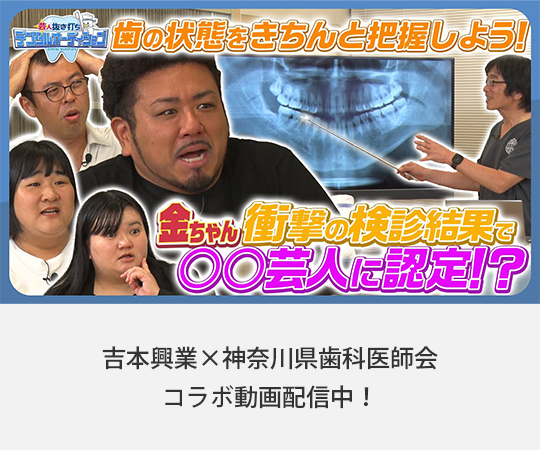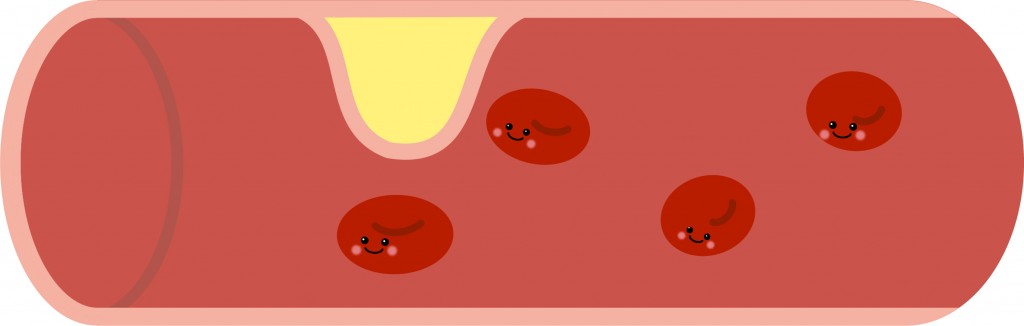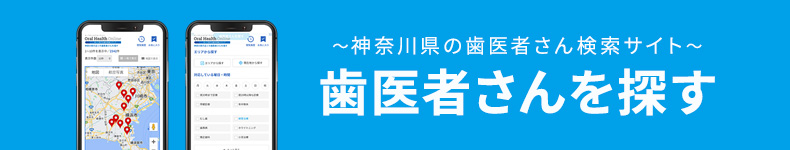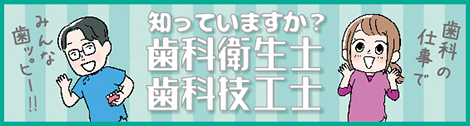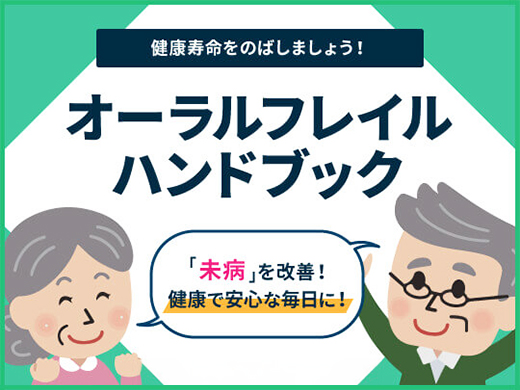口腔の成長と老化
- 執筆者
- 神奈川県歯科医師会・藤沢市歯科医師会会員 小林 哲也
-
 2025/07/07
2025/07/07 - 歯とお口の基礎知識
体には、臓器が存在します。口から食物を入れ、排泄される過程には臓器を通り、食べ物を消化し、栄養を吸収する事によって老廃物を排泄するという一連の流れがあります。その入り口となる臓器が口腔です。
口腔をつかさどる場所は、頭蓋骨や上顎骨、下顎骨、歯牙という硬組織が形成し口蓋や口腔底、舌という軟組織を作り唾液という分泌物が排出されています。外側には、口腔を動かす筋肉と表情をつかさどる筋肉に囲まれ、体では唯一の同時に動く一対の顎関節がある特殊な領域です。下顎骨は唯一、頭蓋骨にぶら下がっている骨で体の重心に影響を及ぼすと言われています。
さて、この口腔はどの様な多くの役割を果たすのでしょうか?
先程も伝えた様に、臓器である為唾液による消化機能を持っています。また、消化し易い様に歯牙と筋肉により物を噛み砕くこともできます。舌や口腔の周りの筋肉により発音を調整し表情を豊にします。その様な口腔が、生まれてから死ぬまでにどの様に変化していくのか順にお話いたします。
『胎児〜乳歯列期』
お母さんのお腹の中で育っている間に、口腔の機能の殆どが出来上がります。お腹の中にいる胎児の顎骨内には、乳歯の卵(歯胚)が存在していますが生まれたばかりの赤ちゃんにはまだ歯は生えていません。出生後6ヶ月〜2歳半の間に乳歯の歯20本が生えそろいます。
出生後は、お母さんの母乳を口の周りの筋肉と舌を使い栄養だけではなく体の免疫機能を左右する抗体も吸収していきます。この頃は、口腔内の細菌嚢は安定せず虫歯菌や歯周病菌はあまり存在していませんが歯が生えてくる頃から菌も増加していきます。
この様に、口腔の周りの筋肉が発達し段々と離乳食から2歳ぐらいには固形食となり小児と変わらない食べ物へと変化していきます。
『口腔の発育とは』
口腔は、歯が生え揃い食べられれば良いわけではありません。
舌や口の周りの筋肉が安定することにより、正しい嚥下、綺麗な発音や歯列、精密な咬合によりバランスの取れた笑顔が出来上がります。また、味覚も含め生活を豊かにしてくれます。
これらは、生まれてから成長し老化してゆくまで変化していきます。口腔の発育は、成長と共に背が伸びるのと平行しながら頭蓋骨や顎骨も成長曲線を描いていきます。「食べ物はよく噛んで」と言われる様に、よく噛むことにより口輪筋や咀嚼筋が発達し顎関節に刺激が伝わり口腔の成長をうながしてくれます。また、唾液が多く分泌され消化にも良いとされています。
また、口腔の発育には阻害因子もあります。その一つは癖です。
指しゃぶりや、寝相などが大きな要素になります。
二つ目は、鼻の病気です。鼻が詰まっていることによる、口呼吸です。常に口を空けていることによって、口輪筋の発育に大きく関わり歯列の不正や口腔内が乾燥する為、虫歯にもなり易くなります。
三つ目は、姿勢です。テレビや食事、勉強の姿勢により首の位置や気道の形が変わってしまいます。
これらは一部ではありますが、口腔全体の発育、発音、歯列、嚥下に影響を及ぼす事になります。
『交換期から永久歯列期』
この頃から、色々な種類の食べ物を選択し食べ、多くの言葉を話し、成長に影響を与える因子が増え始めます。
その為、虫歯ができたり歯を失う事により永久歯が生え揃うスペースが無くでこぼこの歯列になる原因になります。
これらの影響で、噛み合わせの左右のバランスに変化も生まれます。
中高年になると、タバコやお酒による不摂生な生活を送ることにより虫歯菌や歯周病菌も増えていきます。そして、歯を失い義歯やインプラント・補綴物が多くなっていく年頃です。
また、高齢になればなる程口腔の老化も進んでいきます。
多くの歯を失えば、食べる物も変化し老化による味覚の変化により好みの味も変化してゆくでしょう。
その様にして、口腔の老化から表情の老化へも移行していきます。
『まとめ』
オーラルフレイルという言葉を聞いたことがありますか?
フレイルとは、筋肉や心身の活力の低下を意味します。
オーラルフレイルとは、口腔機能低下症とも言いますが必ずしも年齢とイコールでは無く、良く喋り・良く笑い・多くの歯を残す事によって色々な物を食べる事で予防できます。
近年、食については過去100年で大きく変化してきました。
食や社会的影響により、健康寿命も伸びています。
是非、お口の健康や笑顔を維持して健康寿命を伸ばしていきましょう。
- 執筆者情報
-
小林 哲也神奈川県歯科医師会・藤沢市歯科医師会会員
ティーアンドエスデンタルクリニック